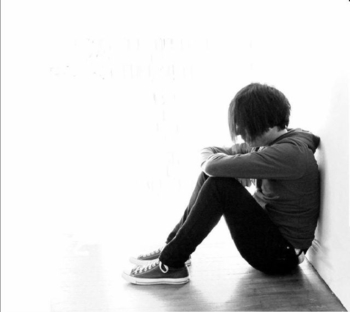🌿 訪問支援のご案内
私たちは、日本全国どこへでもご依頼があればご自宅に訪問し、
お子さんやご家族と直接お会いしてサポートを行っています。
毎年3月・4月は、季節の変わり目とともに環境が大きく変化する時期です。
ひきこもりや不登校の状態にあるお子さんが、
「このままでいいのだろうか」「みんなは進んでいるのに自分だけ止まっている」
という不安や焦りを感じやすい季節でもあります。
その気持ちは、周囲にはなかなか理解されにくいものです。
「置いて行かれた」という感覚から、深い孤独や自己否定の思いに苦しむこともあります。
——だからこそ、この春までに“心が落ち着ける居場所”を見つけてあげることがとても大切なのです。
🎓 通信制高校という選択、そしてその先へ
近年は、通信制高校を選ぶ方が増えています。
登校日が少なく、自分のペースで学べることは大きな魅力です。
しかし、実際にはその途中で通えなくなったり、
卒業後に再びひきこもってしまうケースも少なくありません。
私たちは、こうした状況を「問題の先送り」ではなく、
「次の一歩を見つけるための大切な時間」と考えています。
この3年間をどう過ごすかで、その後の人生の流れは大きく変わります。
周りと関わるのが苦手だからこそ通信制高校を選ぶとしても、
最終的には人と関わる力を少しずつ取り戻さなければ、社会の中で生きていくことは難しいと私たちは感じています。
では、どうすれば関われるようになるのでしょうか。
——その答えを、ご家族と一緒に考えていきます。
🤝 私たちができること
お子さんの性格やこれまでの歩みを丁寧にお聞きし、
「何から始めればよいか」「どんな環境なら前に進めそうか」を、
ご家族と一緒に整理していきます。
ご家族の方も、抱えてこられた不安や戸惑いを遠慮なくお話しください。
ご家族だけでは見つけにくい“次のステップ”を、私たちが共に探していきます。
ひとりで悩む時間を、少しずつ希望のある時間へと変えていくお手伝いをいたします。
さらに私たちは、一人ひとりに寄り添いながら、3年後・5年後の姿を見据えて必要なことを具体的に提案します。
必要であれば、通学に同行したり、就労の場に一緒に立ち会うこともあります。
徹底的に寄り添う伴走者として、そして現実的な道筋を示すメンターとして、
お子さんとご家族に寄り添い続けます。
全国どこでも訪問が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
📞 お問い合わせ・お申し込み
電話:052-564-9844(一般社団法人青年生活教育支援センター)
メール:smilehousejapan@gmail.com
訪問対応地域:全国(北海道から沖縄まで)
対応スタッフ:青木 美久・吉村 敦子・他
一般社団法人 青年生活教育支援センター